認知症という言葉に、どんなイメージを抱いているだろうか。
「物忘れがひどくなる」「日常生活が難しくなる」――そんな固定観念に縛られていないか?
私が出会ったのは、39歳で若年性アルツハイマー型認知症と診断されながらも、自分の言葉で社会に声を届け続ける一人の男、丹野智文さん。
その講演を聞いた私は、「認知症とは何か」という問いを、自分自身の未来として突きつけられることになった。
【丹野智文】
1974年宮城県生まれ。ネッツトヨタ仙台に勤務。39歳の時に若年性アルツハイマー型認知症と診断される。診断後は営業職から事務職へ異動して勤務を続けながら、「おれんじドア」の実行委員会代表を務め、自らの経験を語る活動を続けています。
まず、初めに講演会を拝見して感じたことは普通の人だなという印象でした。初めに若年性認知症だという説明を受けていなければ、分からなかっただろうなと感じた。話し方は結構クセが強かったのだが、認知症の影響というよりは東北訛りなのかという感じがした。
初めに若年性認知症のになった経緯をご自身の口から説明され、その後に質問という形式だったのだけれど、普通に質問にも受け答えしていたし、公演中に不審な行動をされるようなことはなかった。
認知症当事者としての視点
やはり、興味深いのは認知症当事者としての視点だろう。どれだけ医学が発展しようとも精神や脳の病気というのはわからないことが多いのだと思う。実際に症状や体の変化が出るわけではないので、人から話を聞いて診断をするしかないのだけれど、人間というのはウソをつく生き物なので患者本人が本当のことを言っているのかがわからない。高齢者ともなれば、年齢による物忘れや勘違い、古い情報、結晶のように凝り固まった常識など私たちには理解できないものも多い。
そんな中で39歳という若さで認知症当事者としての体験談を話していただけるのはそれだけで貴重である。
冒頭に書いたように話を聞いている感じでは何ら不審に感じる部分はなく、普通の人が話す講演会と変わりはなかったので、認知症の体験談としてすんなりと聞き入れることができたのは貴重な体験だと感じた。
認知症で生活するための工夫
話を聞く中で面白かったのは認知症を抱えながら生活する工夫である。道に迷ったり、スケジュールを忘れたりすることが良くあるそうなのだが、私も同じように道に迷うし、スケジュールを勘違いする。ただ、アルツハイマー型の認知症というのはこの症状が強く出てしまうようで、道に迷ってもそもそもなぜここにいるのかが分からなくなるらしい。スケジュールに関しても予定が入っていたこと自体を忘れてしまうようだ。
そこでこのようなミスをしないようにどうしているのかというとスマホをフルにかつようしているということだ。
道が分からなければ、グーグルマップでピンを立てて知り合いに連絡するらしい。スケジュールはタイマーを毎回セットして、そこにメモを添えて持っていくものや何をするかを書いているという。
何ということはない、私たちも普通に行っているような対策で認知症と向き合っているみたいだ。
最近はさらにChatGPTのような生成AIの使い方を覚えたらしく、困ったことがあればAIに相談しているらしい。今この記事を読んでいるあなたはAIをうまく活用できているだろうか?
認知症であってもAIの使い方をおぼえることはできるし、新しいことを覚えることもできる。ただ、短期間での記憶がなく生活に困ることが多いということのようだ。
まとめ
丹野さんの講演を通して見えたのは、「病とともに生きること」への覚悟と、社会がいまだ見落としている“当事者のリアル”だった。
認知症というラベルだけで人を測ることの浅はかさ。
そして、記憶を失ってもなお、「今ここで生きている」という事実の重み。
誰にでも訪れ得る未来だからこそ、私たちはもっと“当事者の声”を聞き、そこに向き合う視点を養うべきだ。
それは、ただの感想では終われない、自分自身の生き方に関わる問題なのだから。
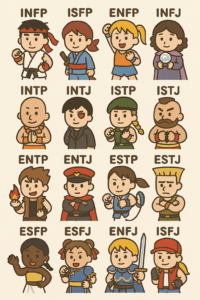
コメント